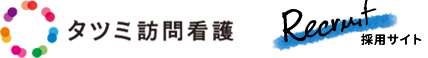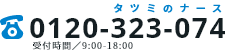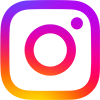お盆はいつからいつまで?お盆の過ごし方について
もうすぐお盆です。「お盆=夏休み」のイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実際にお盆はどんな期間なのかご存じですか?今回はお盆についてご紹介していきます。
・お盆はいつからいつまで?
・地域によるお盆時期の違い
・新盆(初盆)とは?
・お盆の風習
・お盆に行われる全国の行事
お盆はいつからいつまで?
お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言います。ご先祖様や亡くなった家族の霊が私たちの家に帰ってくるとされる期間です。最初に日本に伝わったのは7世紀頃と言われています。
お盆の期間は、一般的に8月13日~16日の4日間です。かつては、旧暦の7月13日~16日(現在の8月中旬~9月初旬)ごろでした。明治6年(1873年)に日本は新暦になり、多くの地域ではちょうど1ヶ月ずらして8月15日前後に行うようになりました。

地域によるお盆時期の違い
新暦7月盆の地域(7月13日~16日)
多摩地区を除く東京や北海道函館市、石川県金沢市などでは新暦の7月が主流です。
旧暦から新暦に切り替わった当時、これを徹底させようと必死に努めていた明治政府に対し、そのお膝元であった東京やその周辺の地域などは令に沿って対応せざるを得なかったため、新暦7月15日にお盆を行なうようになったと言われています。「新のお盆」または「東京盆」と呼ばれることもあります。
新暦8月盆の地域(8月13日~16日)
全国的に多くみられるお盆の期間です。新暦の採用当時、明治政府の目の行き届かなかった都市部以外の地域では昔からの慣習をすぐに切り替えることはせず、旧暦7月15日のお盆が行われ続けました。そして、旧暦7月15日に近い新暦8月15日をお盆とすることで徐々に落ち着いていきました。「月遅れ盆」とも呼ばれています。
旧暦盆の地域(旧暦7月13日~15日)
沖縄や奄美地方では、現在でも旧暦で多くの行事が行われています。「シチグヮチ」とも呼ばれるお盆は「家族を大切に、祖先を大切に」という考えの強い沖縄では、一年で最も大切な行事です。沖縄の伝統芸能「エイサー」はいわゆる盆踊りで、ウークイと呼ばれる3日目に演舞が披露されます。
旧暦に沿っているためお盆の期間は年によって変わり、9月にずれ込む年もあります。

お盆の風習
お盆は地域によってさまざまな風習がありますが、ここでは一般的な例を紹介します。
・盆棚(精霊棚(しょうりょうだな))を準備する
盆棚(精霊棚)とは、お盆の時期にご先祖を迎え供養するための祭壇のようなものです。盆の入りの前日か当日に設置し、お盆期間が終わるまで飾ります。現在は盆棚も簡略化されているものもありますが、一般的には台の四隅に笹竹を立てて縄をはり、台の上に真菰(まこも)のゴザを敷いて上にお位牌、三具足、お供え物などを飾るものになります。
またお盆飾りとして有名なナスやキュウリで作った精霊馬(しょうりょううま)もこの盆棚に供えます。
精霊馬は、ご先祖様があの世とこの世を行き来するための乗り物とされ、キュウリの馬にはできるだけこの世に早く帰って来られるように、ナスの牛にはあの世にできるだけゆっくり戻って欲しいという願いがそれぞれ込められています。

・盆の入り(迎え火)
盆の入り(お盆の初日)、盆棚(精霊棚)の準備が整ったらお墓に出向いて掃除をします。夕方には素焼きの小さなお皿の上で苧殻(おがら)を焚き(迎え火)、盆提灯に火を灯し、火を目印にしてご先祖の霊を招き入れます。新盆(初盆)の際は白提灯を用います。

・2日目、3日目
家族や親族が集まってお墓参りをし、自宅に僧侶を招いて法要をします。法要後に皆で会食をすることもあります。
お盆の間、ご先祖様は精霊棚に滞在すると考えられています。お盆期間中は、盆棚(精霊棚)に供えたお供え物や水などは毎日交換しましょう。
・盆明け(送り火)
できるだけ遅い時刻に送り火を焚き、祖霊を見送ります。地方によっては「精霊流し」や「灯籠流し」などを行います。
お盆の行事といえば盆踊り。ご先祖様の霊をなぐさめるための念仏踊りがルーツともいわれ、そこに豊作祈願や、庶民の娯楽としての要素が加わり、各地でさまざまな形の盆踊りが発達しました。

新盆(初盆)とは?
ここで言う「新盆」とは新暦の盆とは違い、故人が亡くなり四十九日の法要を終えてから初めて迎えるお盆のことを指します。にいぼん、あらぼん、しんぼん、または初盆(はつぼん)と呼びます。
故人が亡くなってから初めて家に戻る新盆。しきたりは地域によって異なりますが新盆は通常のお盆法要と異なり、ご遺族の方だけでなくご親族や故人と親しかった友人や知人を招いて盛大に行われることが多いです。
お盆に行われる全国の行事
お盆には各地で伝統的な行事が行われています。ここでは特に有名なものをいくつかご紹介します。
五山の送り火(京都)
京都の夏を代表する伝統行事の一つで、例年8月16日に行われます。その起源は、平安時代とも室町時代とも言われ、お盆に帰ってきたご先祖様の魂を再びあの世に送り出す「送り火」と同じ意味があります。
まず東山に「大」の字が浮かび上がり、続いて松ケ崎に「妙」「法」、西賀茂に「船形」、大北山に「左大文字」、そして嵯峨に「鳥居形」が順番に点灯されます。

精霊流し(長崎)
毎年8月15日に行われる精霊流しは、お盆前に他界した人の遺族が故人の霊を弔うために手作りの船を造り、船を曳きながら街中を練り歩き、極楽浄土へ送り出すという長崎の伝統行事です。各家で造られる船は大小様々。長く突き出した船首には家紋や家名、町名が大きく記されます。
当日は夕暮れ時になると町のあちらこちらから「チャンコンチャンコン」という鐘の音と、「ドーイドーイ」の掛け声。爆竹の音が鳴り響き、行列は夜遅くまで続きます。
日本三大盆踊り(秋田/岐阜/徳島)
盆踊りはお盆の時期にお迎えしたご先祖の霊をもてなし、一緒に過ごして送り出す行事として日本全国で行われています。中でも伝統があって規模の大きな秋田の「西馬音内の盆踊り(にしもないのぼんおどり)」、岐阜の「郡上踊り(ぐじょうおどり)」、徳島の「阿波踊り(あわおどり)」は「日本三大盆踊り」と呼ばれています。

まとめ
今年のお盆も家族や親族で集まることは難しそうですが、古くからのしきたりを大切に、ご先祖様や家族のことを考えながらお盆を迎えてみてはいかがでしょうか。